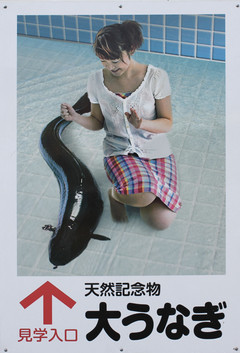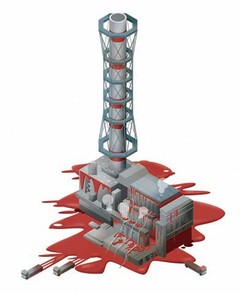4月16日に地元の公民館で行われた「平成23年度永吉校区歓迎会」。僕も今年から小学生の父親になったので初めて出席してきました。今年度から永吉小学校に転入されてきた先生方を迎えての約2時間〜会費千円で飲み放題食べ放題。父兄や学校関係者だけではなく、地域の方々がまんべんなく出席していた様な印象で、公民館の会議室はかつて見た事もない程の人で溢れていました。永吉という村は、昭和の合併時(1955)に伊作町と合併して「吹上町」になり、また平成の大合併(2005)では伊集院、日吉、東市来と合併して「日置市」になりました。合併を重ねるごとに「町の外れ」になってきていますが、かつては町の中心に位置していた歴史のある永吉小学校だけあって、住民の結束力は固い地域だと言えます。当日、会場でお年寄りから「子供は地域の宝」というお話も聞きました。当たり前の言葉なのかも知れませんが、実際に、今でも小学校に対する期待を持ち続けて、会場に足を運ぶというのは並大抵の事ではないと思うのです。ただ、こうした潜在的な力があるにもかかわらず、全校生徒は48名(複式学級を含むので4クラス)という小さな学校になってしまいました。
今回の震災を受けて、地域と学校のつながりが見直されようとしていますが、モデル地区として全国の人に見てもらいたい雰囲気でした。ただ、こうした様子というのは記録されにくいし、ブログでも伝えにくいんですね。
今、コンパクトシティ構想という考え方があって、街の中心部に主要な施設や住宅を集める動きが目立ちます。日置市でも、合併後市役所の周りが賑わいを見せてきました。勿論、良い面もあるでしょう。しかし本当の弱者はどうするのかと言った問題は解決出来ない筈です。田舎にも市営住宅を造って住民を増やす考え方もある様ですが、定住を促進させるためには、古民家を安くで買い上げて市がリフォームする方が安上がりですし、都会の人の期待に応えられると思うんです。都会の人は、わざわざ田舎で集合住宅に住もうとは思わないでしょうから。田舎にあって都会にないもの、或いはその逆を補充し合う。311以降の価値観は、そうした複雑なパズルを比較的簡単に組み上げていくのでは?と期待しています。自分も出来る限り発信していきたい。それにしても、こうした問題に立ち向かう専門家はいないんでしょうか?都市計画を勉強している若い人(数名の顔が浮かんできます)たちとか?
***
4月17日には、その小学校の前で年に二回だけ開催される「木市」に出かけてきました。昔はしょっちょう市が立っていたらしいのですが、こうした歴史も僅かに残っています。サクランボとイチジクの苗木を買って、早速庭に植えました。枯らさない様にガンバロウ。