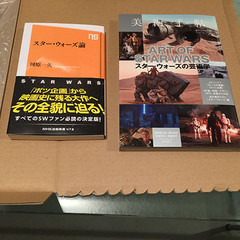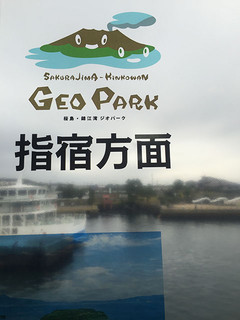11月14日。私が暮らす地域の中心的存在「永吉小学校」で図工の授業を担当させてもらいました。いろいろと考えた末に「デジタル表現をアナログで」という課題を与えてみました。色のついた1センチの方眼紙(5色分)を与え、方眼(グリッド)以外の部分でカットすることを禁じた上でキャラクターを数体作らせます。これが一時限目。二時限目は、大きな方眼紙を教室の前と後ろにある黒板に貼りだし、それぞれが作り出したキャラクターに関係性を持たせてみました。この時もグリッドに沿って貼り付けることを指示しました。途中から制御が効かなくなり、最終的には斜めに貼り付けられていたりしますが、まあこれはご愛嬌・・・。
僕はデジタルの恩恵を受けて生活していますが(もちろんみなさんも)、結局は「正確に情報を伝える術として優れているから」ということが一番の魅力なんだと思っています。永吉小学校の生徒には、授業の終わりに「この作品は紙としての寿命が来るけれど、どのグリッドにどの色が塗られているか、ということを記録しておけば、100年後にこの状態を再現できるよ」と言ったんです。果たして、どこまで通じたのか解りませんが、写真、音楽、絵画、テキストetc・・・全てを差別せずに受け入れているメディアっていうのは、やはりすごいことですよね。