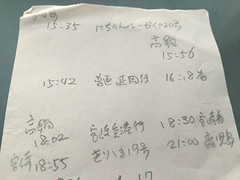Nissan Leaf(その12)を書いたのが昨年の8月なので、随分と間が空いてしまいました。昨日、とある知人から「結局どうなのよ?」という質問を受けたので、計算してみることにしました。年間1万キロ以上は走るのですが、現在の平均電費(燃費ではない)が、8.2km/Kwと表示されています。勾配が多い鹿児島ですから、平坦な都市部を走るよりは若干パフォーマンスが悪いと思われます。
で、実際に1万Km走るのに、10000÷8.2=1219.5 → 大体1220〜1220kwを使っていることになりますね。深夜電力で充電しているため、1kwが幾らかというと、九州電力の伝票から計算すると 1kwが10.3円くらいの様です。ということは、1万キロ走るのに、10.3×1220=12444円。
これを、うちのもう一台のガソリン車・・・燃費が12キロ、ガソリン1リットル150円で計算すると・・・10000÷12=833 833×150=124950円。
ほぼ10倍の価格差が出ました!1万キロ走ると、112506円エネルギー代が浮くことになります。
導入前も、約10倍くらいの差はあるという噂は聞いていましたが、嬉しい結果ですね。
(算数・数学に弱いので間違いがあったらツッコんでくださいね〜)