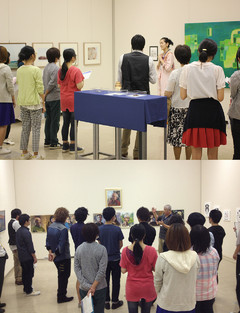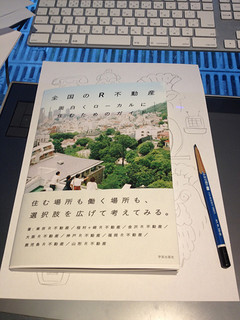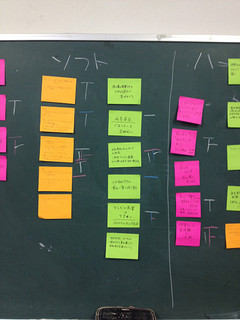自宅の敷地内で、昨日から毛虫が大量発生しています。22時頃帰宅したところ、玄関の電灯に集まっていました。高いところに登るのは苦手な様で、何故か地面を這っているんですよね。近所の友人宅でも目撃証言があるので、悩まされている人は多いかも・・・。ネットで検索したところ「フクラスズメ」という蛾の幼虫だそう。「カラムシ」(植物)を食べるということなので、草払いを徹底してしたらこんなに発生しなかったかも知れません。15年ほど住んでいますが、こんな事は初めて。子供に「大変なことになってるぞ〜」と報告したところ、面白がってどんどん捕獲して・・・こんな状態に。サイズが大中小・・・、個体差があるのが不思議ですね。まあ、パッと見、気持ち悪いですが、自然界では何らかの役に立っているのだろうと思います。