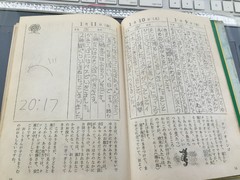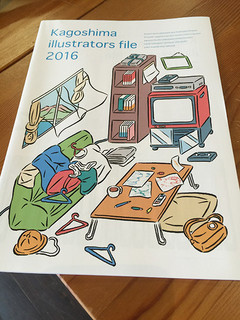武蔵野美術大学校友会・鹿児島支部の有志が集まり、毎年行われている自由な展覧会「む展」。今年の会期は7月12日(火)〜17日(日)の6日間。場所は鹿児島市立美術館です。5月28日に第一回の実行委員会が開かれました(写真)。今年のイメージ作りを担当されているのは、デザイナーの花田理絵子さん。「聞こえる造形×見える音」というテーマでポスターやDMなど広報ツールをただいま作成中。会期中に花田さんがリコーダー奏者として活動している「柳田合奏団」の演奏も計画されています。
権威主義を否定し、毎年、新しい試みをちょっぴり取り入れたり、新人が入ってきたり・・・と新陳代謝を繰り返しているのがむ展の特徴でもあります。僕も、今年は初めてラフスケッチを大量に展示しようと考えています。今から予定表にチェックを入れておいてくださいね。