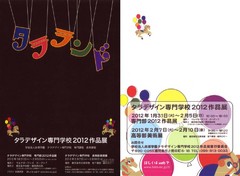
明日1月31日から2月5日まで、タラデザイン専門学校の終了制作展「タラランド」が行われます。会場1は「マルヤガーデンズ」7Fの「garden 7」会場2は鹿児島中央駅の「一番街商店街・いっど」となっております。
僕も、週に一度ですが、イラストレーションゼミの授業を担当させて頂いています。途中経過は何度かチェックしましたが、果たしてどんな仕上がりになっているのか・・・今からドキドキしています。
皆さんも鹿児島の若い感性に、是非触れてみてください!どうぞよろしくお願いいたします。
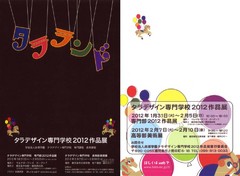
明日1月31日から2月5日まで、タラデザイン専門学校の終了制作展「タラランド」が行われます。会場1は「マルヤガーデンズ」7Fの「garden 7」会場2は鹿児島中央駅の「一番街商店街・いっど」となっております。
僕も、週に一度ですが、イラストレーションゼミの授業を担当させて頂いています。途中経過は何度かチェックしましたが、果たしてどんな仕上がりになっているのか・・・今からドキドキしています。
皆さんも鹿児島の若い感性に、是非触れてみてください!どうぞよろしくお願いいたします。

仕事の合間を縫って、今週はムカデを描いております。「百足」と書いて「ムカデ」とする漢字は大げさな例えで、実際は40本しかありませんね。しかし、1本1本描いているので、なかなか終わらず・・今ようやく36本目にこぎ着けました。先日、たまたま観たNHKの番組では、若冲が鶏の羽をどう表現したのか?なんて話題が取り上げられていましたが、まさに、そうした先人達のテンションをどう乗り越えられるか?というのがひとつのテーマでもあります。江戸時代はフォトリアルという概念自体がなかったから、精密に描けば描くだけ意味があったんでしょうね。今は価値観も多様化したので、写真っぽいとか、下手とか上手いとか、単純な評価軸では語れない複雑な時代です。しかし「熱意そのもの」というのは、テクニックうんぬんを超えて、ごまかしようなく、絶対に通じる筈だと信じて創作するしかありません。
話題は変わって「最近、メジロやスズメを見かけなくなった」という投書を南日本新聞で目にしました。それが、88歳と91歳のおじいさんからのものだった。僕よりも倍の冬を体験しているので(なおかつ今は静かな暮らしをしている・推測ですが)、特にこうした異常事態についての「アンテナの張り具合」のレベルが違う。原因は、桜島や新燃岳なのか、はたまた放射能なのかわかりませんが、メジロはうちにも来ないですね。自然の事については、若冲もそうだし、鳥の事を気にしているおじいさん達もそうですが、とにかく、昔の人の話を聞いた方がいいかも知れません。

長男(小学1年)の冬休みの宿題のひとつに「凧作り」があったのですが、どんなタイプを作ろうかと悩みました。学校側から渡されたプリントにも何案か作り方が書いてあったのですが、ネットで調べた結果「簡単シンプル凧」に辿り着きました。材料さえ揃えば、本当に簡単に作れます。僕と息子で、それぞれ1つずつ制作。
早速、徒歩3分の空き地でテストフライト。70メートルの凧糸がほぼなくなる程よく上がりました。空き地、というのは正確に言うと夏場は田んぼとして機能している場所です。凧上げが冬場行われる意味が、体験として初めて解りました。それにしても凧上げをする子供の姿を見かけることはないですね。田舎に住んでいても結局は室内でゲームなのかな。僕が小学生の頃、ゲイラカイトの上陸によって凧上げブームが起きた記憶があります。それまでは和凧・・奴凧を普通に飛ばしていたんですが・・・。そういえばその頃、ウインドブレーカーも流行りだした。石油化学製品が台頭してきた時期と幼少期の想い出がリンクしているっていうのは、僕らの世代ならではでしょうね。

昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と追記を本ブログで紹介していきます。
***
あいさつから始まる未来社会
「おはようございます」「おはようございます」私の暮らす地域では、幼児からお年寄りまで、誰もが道で出会えば挨拶を交わす。時には、走っている車に向かって立ち止まり頭を下げている様子も見られる。 一方、首都圏では防犯上子供には「知らない人は無視する」という教育をする地域もある様だ。挨拶が作り出す安全もあるのだが、皮肉な世の中である。私も東京の集合住宅を転々としていた時期、引っ越しの挨拶として用意した菓子折りをドア越しに受け取り拒否された経験や、「五月蝿い」と同じ住宅の誰かに警察を呼ばれた事がある。通報者が解れば、謝罪のしようもあるが・・・。これでは、地域や社会に対して萎縮せざるを得ない。
地縁、血縁といったものが持つ独特の「煩わしさ」を後回しにする事で、いや、最も単純な「挨拶」をも敬遠することで近代の日本は「経済的に」成長してきた。しかし震災以降は「お金でない何か」に立ち戻ろうとする気配が感じられる。これからは日本人が根源的に持つ関わりの価値が見直されて行く筈だ。盆暮れ正月だけ「モラトリアム人間から脱却する」という働き方はスマートではなくなるだろう。
先日、初めて地元の小学校の運動会に「おやじ会」の一員として参加した。終了後、 地元の商店が用意した屋外のお座敷で教職員の方々や保護者との慰労会があった。 涙と笑いに溢れた宴は、二次会にまで及んだ。会場は何と校長先生のお宅である!全校生徒48名という小さな学校だが「地域との連携」は全国のモデル地域になるのでは?と思える程。いわゆる「郷中教育」の風習も残っており、毎年12月に同じ集落の住民と語り合う機会がある。会場は持ち回り制で自宅を開放する。
両者とも都会では考えにくい状況だが、個人情報保護や法令遵守などでギスギスしている社会とは対極にある光景で気持ちがいい。「絆」という表現は好きではない。もっと大らかな空気が流れている。そこに私は未来を見ている。
***
追記:
都会の人には「近所付き合いが大変なのでは?」という質問をされる事があります。都会でも地域コミュニティを視野に入れた分譲マンションが人気を集めているそうですね。震災以降は、地域活動と政治参加で「自分の暮らす街を育てる」という意識がより一層強まったのではないでしょうか。

ロボット怪獣「クレージーゴン」(Amazonでクレイジーゴンと入力したら「もしかして:クレイジーケン」と表示されます。ちゃうって!)。昨日、専門学校の授業の帰りにぶらりと立ち寄った某古本屋さんで発見、100円だったのでタッコングと2体同時購入!息子が平成ウルトラシリーズを見始めた頃、僕はやはりウルトラマンやセブンの事も知ってもらいたかった。そんな訳で、迷わず最初に買ったDVDが「ウルトラセブン」にこのクレージーゴンが登場する「vol.10」だった(第38話)。何といってもロボットで怪獣でクレイジーでゴン(?)ですから、もう、スゴイことになっています。車をどんどん飲み込むサマが圧巻。どう見てもミニカーなんですが、CGよりも脳内補正的にはリアルに感じられるから不思議ですね。

昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と補足説明を本ブログで紹介していきます。
***
個性という厄介なもの
「思っていることを行動に移す事が出来ない」場面は誰にでもあるだろう。多くの場合「自分という存在そのもの」が壁となって立ちはだかっている。果たして自分はいるのだろうか?
子供の頃、 手鏡を片手にずっと瞳の奥を見つめていたことがある。自我が芽生えてきて、その不思議さを確かめるために覗き込んでいたのだと思う。あらゆる景色の中で最も特殊な場所だった。そのうちに怖くなって、自分が「いる」のか「いない」のか解らなくなった。高校生になり、私は放課後の殆どをデッサンに費やした。仲間と同じモチーフに対峙して、描き終えた後、ズラッと作品が壁に貼られる。同じ石膏像を描いていても異なる結果が投影される。当然、先生からの講評を受け、他人や参考作品と比較される。そんなある日、指先・鉛筆から紙へと自分の考えを伝える動作そのものが、脳細胞を増やしたり結びつけている様子が解った。以来、画面を通して自分を見つめる日々が訪れることになる。勿論、今でも自分に対する問いは続いている。様々な作風で「自分とはこんなものか?」と敢えて揺さぶりをかける。 しかし時代性や国民性から解放される表現を目指しても、その枠組みを越えるのは難しい。
ここで重要なのは、受け手側から見た場合「自分を変えよう」と意識して制作した様々な試みの共通項に、自分の個性が宿っているいう事だ。つまり、本当の自分というものはコントロール出来ない領域にいる。スピルバーグらしさは「ジュラシックパーク」と「シンドラーのリスト」に共通する部分と言えば解りやすいだろうか。
自分など存在しないと強引に決めつけ行動し続けたとき、初めて成果がズラッと並ぶ。具体的な事、抽象的なもの・・・その質はいろいろとあっていいが、量は多い方がいい。それを第三者が俯瞰で捉えたとき、個性というものはようやく浮かび上がってくるのだと考えている。「無私」というのは鹿児島のキーワードでもある。
***
追記:全13回の中で最も伝わりづらかったと思われる一編です。専門学校で、授業には出席するけど課題を出さずに聴講だけしている学生が何人もいます。特に表現をする世界では「参加してナンボ」ですので聞いているだけでは殆ど意味がありません。恥ずかしいと思っても、とにかく発表すること。自分も、5年前、下手をすると半年前の作品でさえ恥ずかしくなる事があります。だけどそれは発表したから恥ずかしいのです。恥ずかしさが次のステップへと繋がるんですよね。
(画像は17日に江口浜から見た東シナ海。iPhoneで撮影、色調補正など加工はしていませんが、本当にこんな風景でした。)

昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と補足説明を本ブログで紹介していきます。
***
仕事と視線について
「イラストレーター 大寺聡」と書かれた名刺を差し出すと「普段は何をされているんですか?」という反応が返ってくることがある。また、デザイナーと間違われる事もしばしば。確かにデザイン領域での仕事だが、立場としてはカメラマンと同じで、デザイナーとは反対である(正反対ではないが)。「依頼主が観たいと思う情景」を具現化するのがイラストレーターの役割。印刷、或いはテレビやインターネットなどを通じて不特定多数の相手にメッセージを届ける。言われるがままに描くのか?というと、そうではない。勿論自分の感覚を上乗せしたり、場合によっては「ここは必要ないのでは」という引き算の交渉をして、誰もが理解しやすい絵を共同作業で仕上げていく。
「作品にかけた時間」と同じ時間を受け手が費やせば、作家は報われるという話を聞いたことがある。画家の場合、10年を費やした大作が美術館の常設展示にでもなれば、5分間鑑賞する人が何千、何万と増える事で報われる事になるのだろう。これに対しイラストレーションの寿命は「ひと月程度」である場合が多い。画家とは違う。しかし1万部発行される雑誌の片隅に自分のイラストが掲載された時、読者の視線が5秒ずつに注がれれば、積算で約14時間。そこにやり甲斐を感じる。
資格は必要ない、誰もが自己申告でイラストレーターになれる。幸いにしてこの仕事一本で生活していられるのは、様々な視線がーそれが無意識的であるにせよー自分の背中を押しているからに他ならない。
近代画家を多数輩出した鹿児島。現在でも世界に通じるセンスを持ち合わせている若者が潜在的に多い。作家側の水準を上げる努力は勿論だが、その才能が開花するためには「デザインに対する一般の方々の興味が広がるかどうか」にかかっている。農畜産物では、既に高いブランド力を持っている。同様に「鹿児島のデザインってイイね」と全国から視線が集中する時代は果たして来るのか?
***
追記:
アートとデザインが混同されて語られる事が多くなってきました。その線引きは、自分の中で明確にしていたい。仕事の内容を断片的ではありますが表現してみました。鹿児島にもいろんなアートシーンやデザインのレイヤーがありますが、そのひとつひとつが閉じられた世界を形成してしまうのは一番良くない。権威主義的になってしまったり。そうした閉塞感が限界点に達して鹿児島を離れる人もいる。「南点」を振り返る(01)で語った事とも繋がりますが、自分の感覚を多極化すれば乗り切れる話・・・僕はそんな訳で美術団体には属さないことにしています。農畜産物の話を例に挙げていますが「外貨を獲得している」という部分が重要です。鹿児島を拠点に、全国(或いは世界)から仕事をもらえるような動き方をすればいいと思っています。自由に働きたい、という話なんです。

親戚のRおじさんとMおばさんの家庭菜園で採れた大根!あまりの可愛さにいてもたってもいられなかった様で、オーテマハウスでのお披露目会となりました。これは、紹介しない訳にはいきませんね。この手の話題は、よくテレビや新聞で見かけますが、やはり手に取ってみると愛着があります。しかもビバンダム君のガッツポーズにしか見えない・・・。きちんと前、後ろもある。そんな訳で別アングルからもお楽しみください。ちなみに、下半身(大根にとっては上半身)は、既に調理済み?のためか垂直面でスパッと裁ち落とされておりました・・・。


昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と補足説明を本ブログで紹介していきます。
***
立派な家
私が暮らす日置市吹上町に「立派な家」がある。車中から眺める度、心を奪われている。とはいっても高級感のある住宅でもなく、タワーマンションでもない。こじんまりとした母屋と、同じ様なスケールの蔵が二棟並んでいて、全て瓦屋根の木造。手前には井戸、適度な大きさの水田と家庭菜園、背後には照葉樹の森と杉林が広がっている。
私の様な素人がパッと見ても「自給自足に近い暮らし」が実現されている事が理解出来る。何よりもそのスケール感が丁度いい。 電気だけはやむなく引いているのだろうが「暗くなったら寝ればいい」そんなメッセージを静かに発信し続けている様だ。
このように本来、庭というのは食糧とエネルギー、更には建築材料をも確保出来る重要な場所だったが、 近代国家を実現するために日本人は「庭とそれにまつわる知恵」を放棄していった。集合住宅における効率的で便利な暮らしが、経済発展という目的のために正当化されてきた。「誰かに依存する事」によって自由な時間を得て、様々な仕事が生み出された。そうした構造を軸に奇跡的な発展を遂げてきたのだ。
しかし1993年をピークに国際競争力は下がり続けている。更なる上のステージがあると信じてハコモノや道路を造り続けた。こうした全てのツケが、東日本大震災であぶり出される結果に。「経済発展しなければいけない」という幻想は、生理的に信じられなくなっているのに「お金がないと暮らせない」という矛盾を誰もが抱えている。
例えば「自給自足度の割合に応じて税金優遇措置がある」という価値観にシフトする。昔の様に、お金がなくても暮らせる社会に一人一人が立ち戻ろうとする事で、国家の無駄遣いも減っていく。
集合住宅で育った私は、鹿児島に移住して初めて庭の意味が解る様になった。「家庭を築く」という言葉は「家プラス庭」という、日本人の「身の丈に合った暮らし」を差しているのではないか。
***
お正月のNHKの番組で「里山資本主義」という言葉を初めて知りました。放置されている山の恵み、あるいは廃材を使って、食糧やエネルギーを確保したり、観光産業を生み出したり。まさに今、そんな時代を迎えているのだと思います。

新春早々、ネットに繋がらなくなるというトラブルが発生。iPhone上でメールが読めるので、慌てる事はないけれども事業には差し障りがある。パソコン上の設定の問題だと思ってアレコレやっていたが、どうにも上手く行かないのでこれはハード的な問題だと勝手に判断。ADSLモデムで、いつもはチカチカと点滅しているランプが、電源ランプ以外は消えている。以前からおかしいと思っていたのでサポートセンターに電話してみると、早速担当のSYNAPSEのSさんがやってきてくれた。以前、この地域にブロードバンドを誘致する際に大変お世話になった方。すぐにモデムを交換してもらい、無事にネット接続が出来る様になった。それにしても、30キロ以上も離れた場所からわざわざ来て頂いて・・・恐縮でした。田舎は不便だと思われがちだけれども、今回の様に熱意のある人に支えられています。どうも有り難うございました。