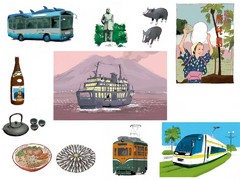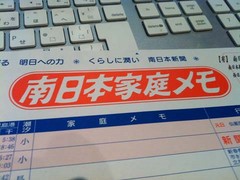「しりんとり」。最近、我が家で流行っている遊びなのです。僕が考案しましたが、これまでに誰かが考えているかも知れません。これまでの「しりとり」では最後に「ん」がつく言葉を言った人が負け、な訳ですが、この「しりんとり」では、最後に「ん」がつく言葉しか使えません。「しりとり」で仲間はずれにされていた言葉に対しての救済措置と言える画期的な遊びです。例えば最初の人が「ところてん」と言ったら・・・「てもみん」(?)-「みかん」-「かけざん」-「ザックジャパン」(←いきなりネタが新しい)-「パン」-「パイプオルガン」という具合に、「ん」のひとつ手前の音で始まる言葉を探していきます。「ん」で終わる言葉って、意外と沢山ある。どうやったら負けか?というのは、NGワードなどを決めるなり何なりと・・・各自適当に考えてください。春休みまっただ中、スペースワールドやTDRなどでの待ち時間に是非チャレンジしてみてください。