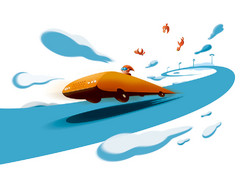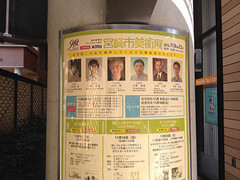「昨日の川内原発に係る住民説明会で、県民は(再稼動についての説明を)理解したこととする」
本当にそれでいいのでしょうか?
質疑応答後、壇上に上がって会場の皆さんにメッセージを伝えていた方からメールをいただきました。以下、全文ではありませんが転記いたします。
ーーー
県の原子力安全対策課に、今回の説明会でアンケートを取らないことについて電話しました。
今回の説明会の位置づけは、
「前回の5会場での説明会の補完として、住民から多かった意見について説明するため。だからアンケートは取らない」
つまり、今回は県民の意見を集約して、県として再稼働の判断の材料とするために開催するというわけではないということです。
それは、今回の説明会が終わったら、
県として「住民に対する説明は終了する。県民は理解したこととする」
という意味です。県議会の判断手続きに入るということです。
ぼくは、質問でマイクをもらって「説明会の延長、あるいは再度開催」
をお願いしようとしていました。しかし、叶わなかった。
説明会が終わる=「ぼくたちが理解したことになる」
のは、なんとかして避けたい。
ですから、物理的に説明者が帰るのを止めるために上がりました。
ひとりなんで、すぐに排除されるとはわかってましたけど、
もうそれ以外は思いつきませんでした。
もっと圧倒的に大多数の人が、
ポーズだけじゃなく、いっしょに止めてくれたら、
見える絵も違うし、実際に変えられるんですが、
難しかったです。
他にあの状況をどうすればよかったのか、
ぼくはわからないのです。
どうすればよかったのか、実際にいい方法があったら、
教えてくれるだけじゃなくて、実現して欲しいです。
ーーー
以上です。
みなさんの一人一人の力が必要です。どうぞ宜しくお願い致します。