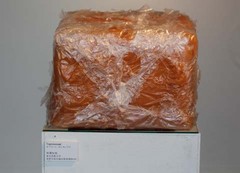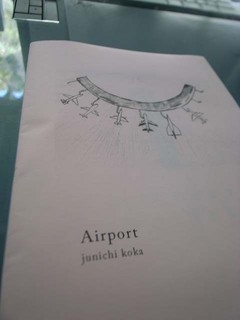昨日、東京からとある文化人の方がお見えになった。「東京って何なんだろう?」と、印象的に語っていた。僕は移住を勧めた。話を聞くと、東京では今回の震災も「最悪の事態を乗り切った」というムードがあり、東京を離れる人の事を「いくじなし」と呼ぶ風潮もある様だ、ごく一部の現象かも知れないが。こんな事態でもまだ原発を必要とする都民は半数以上いるというから、いかにマトリックスの様なヴァーチャル世界なのかが伺い知れる。連日、ネット上で動画を見て、放射能に関する悩みは当分続くであろうと確信している。やはり、広瀬隆氏のインタビューには説得力がある。鹿児島も原発を抱えているから(その部分については)諸手を挙げて迎え入れる様な場所ではないかも知れない。ただ、今現在放射能の心配はないから、友人には「日置市で良かったら物件を本気で探す!」と連絡をしているところ。「人のために何が出来るか?」という言葉がここのところ目立つ様になってきているが、自分にとっては、今は友人に声をかけずにはいられない。キレイごとではなく、まずは自分のためにもそう言わざるを得ない状況。「オンザウェイジャーナル」において町田徹氏は、西日本への民族大移動が不可欠なのでは?と語っていた。被災者だけではなく、何事もなかった人たち、特に子供を抱えている家庭には本気で考えて欲しい。「仕事がない」というのが、移住して当面の悩みになるかも知れない、しかし、もし職を持っていたら会社の上司に「遠距離・在宅勤務」が可能かどうか相談して欲しい。僕はこの12年間、それをテーマに暮らしてきた。きっとうまく行く。イラストレーターだから出来たのではない。そう考えているから出来ただけで「一般的な事務職ほど可能性は高い」とさえ思う。ビデオ会議も出来る。頭の柔らかい社長なら「支所がひとつ増える」といった感覚で社員を放り出して欲しい。今、日本人の知恵を一極集中から多極分散型へ、エネルギーだけでなく、人材もスマートグリッド型へ配置し直さないといけない。物件、本気で探します!