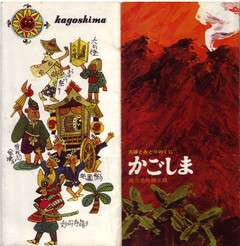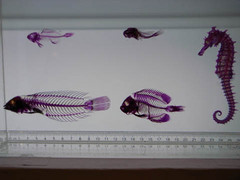昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と補足説明を本ブログで紹介していきます。
***
就職「しない」活動のススメ
私は1990年に大学を卒業した。就職には困らなかった時代。浮かれた世間に馴染めなかった私は「入社したら人生終わり」という考えの下、単位は2年生までに取得、残りの時間は全て「就職しない活動」に充てた。作品ファイルを持って様々な企業や尊敬する同業者を回った。「こんな仕事がしたいんです、こんなイラストを描いています」と必死だった。アルバイトをしながらイラストの仕事を徐々に増やしていき、完全に独立出来たのは28歳の時。それまでは親戚から「30を過ぎると公務員になれないから、そろそろきちんとした方が」とアドバイスを受けたこともあった。「絵では食えない」というのは一般論、しかし実際に動いているから人からは、そんな話は聞かない。
入社したいという学生は、この不景気下で増えている。大企業や公務員が相変わらずの人気の様だ。しかし年功序列や終身雇用制は既に崩壊。公務員も減る。ついでに、完全失業率という数字で豊かさを図るセンスも終わりだ。
職能を獲得する機会は無限に作り出せる。しかし教育の過程で、或いは 友達とゲームや部活をやっている間に「原始的な閃き」「自分の根源的な力」が減衰してはいないだろうか。若い時ほど、敢えて孤独な時間を設ける事が大切だ。
入社試験を50回受けるエネルギーがあれば、自分がやりたい事をファイルにまとめて、いろんな人に可能な限り話を聞いてもらったら?100人に会えば、1人が協力してくれるかも知れない。私が学生の頃にはパソコンはなかったが、今ではネットで海外と仕事を始める事も可能だ。既得権益の指定席はもう満員、キャンセル待ちするより空席を探す方が遥かに創造的だ。操縦士になってもいい。
「きみは一人じゃない」という甘い言葉が巷に溢れている。しかし、独立や起業を目指す若者が増えなければ、日本は旧態依然としたままであろう。
***
追記
1月6日に批評家の井原慶一郎さんと「仕事」について対談をする機会があった。井原さんの提案で、西村佳哲著「地方で生きるということ」をベースにしながら話を進めていった。僕のような自営業者は、様々な人の協力がないと成り立たない。そういう方たちへの感謝を忘れずに、なおかつ、甘えてはいけないという事を肝に銘じながら働く必要がある。原子力エネルギーに代わり、何を選択していくのか?という話もこの日に持ち上がった。大きな仕組みとしての代案を待つよりも「自分で何とかしよう」という行動、「少なくとも家族の分は」という単位が積み重なることが大切になってきていると思うんです。鹿児島には「仕事と彼女、自分で探せ!」という名コピーがありますが、「仕事とエネルギー、自分で作れ」という局面を迎えたのではないでしょうか。