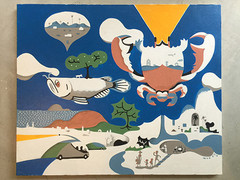昨年12月18日に公開されたスターウォーズの7作目「フォースの覚醒」を
字幕版2回、吹替版2回を鑑賞しました。ブルーレイも発売され更に自宅で鑑賞1回したので・・・そろそろかなあと思い、感じたことをネタバレのない範囲で率直に書こうと思います。
・結論から言うと、シリーズ中では3番目に好きな作品となりました。順番で言うと4-5-7-6-3-2-1。
・ジョージ・ルーカスが監督した新三部作(1999年・2002年・2005年)に対するファンの複雑な思い(主にガッカリという意見!)を払拭するべく、1km先の針に糸を通すような、かなりの精度で脚本や演出が練りに練られた密度の高い作品。
・今回、監督したJJエイブラムス(以下JJ)は僕と同世代の作家。スターウォーズ(以下SW)には特別の思い入れがあるということがダイレクトに伝わってきました。
・JJが監督すると聞いた時に、SWファンは戸惑いを見せていたのも事実。しかしその心配はどこへやら・・・大傑作だと感じました(ただし、二回目鑑賞時に。この件については後述します)。僕も多くのSWファン同様、JJに対しては不安を抱いていたんです。特に彼の監督作「スーパー8」(2011年)のスピルバーグ風味に徹しすぎた演出がその大きな原因。これをSWでやられたらたまったもんじゃない、という危惧があったんです。「スーパー8」の表面的なSF感は、同時期に公開された(オタク視点で)同じようなテーマを扱った「宇宙人ポール」と対極にあったので特に際立ってしまったのかも知れません。しかしJJの感覚を全て否定している訳ではなく、「スター・トレック/イントゥダークネス」(2013年)などは最高に好きな作品です。多くの人材がいるであろう米映画界で、SWとスター・トレックの(ファンにとってみれば)大きく異なる二つの世界観を監督したというのは、大きな出来事だと感じますね。彼の作家性は「仕切り直しでこそ活かされる」ケースが多い。自分たちの世代は、こうした基軸で創作活動せざるをえない側面があるので羨ましい立場だと言えます。(続く)