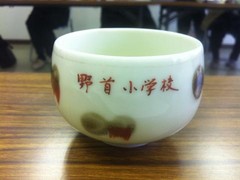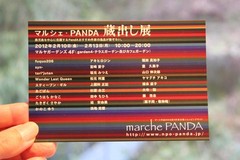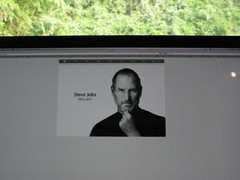昨年、南日本新聞に掲載された「南点」(全13回)を振り返ってみようと思います。約800字という制限の中で言いたい事が伝わったのかどうか。読み逃した方々へ向けて、全文と追記を本ブログで紹介していきます。
***
未来の交通像とは?
毎年、天文館までの距離が遠くなる。郊外で暮らす人の多くはそう感じているのではないだろうか。近くのバス停から山形屋までの直通バスは2006年に廃止された。自分も運転が好きな方ではないから、歳を重ねるごとに更なる「交通弱者」になることを実感している。
もともと、中心市街地というのは公共交通機関によってアクセスされる事が大前提で作られている筈。ところが自家用車の増加に伴い渋滞が発生し、市電の路線は縮小された。しかも、駐車場が確保出来ない昔の中心市街地は来客数が減り、シャッター商店街化してしまった。
しかし今後、交通弱者は増加の一途。これまでの構図は塗り変わる。早急に公共交通機関の未来像を考え、実行する時期だ。 鹿児島では馴染み深い市電だが、世界的に見ると路線はどんどん伸びている。ライトレール・トランジットやトランジット・モールという呼び名で市街地の再活性化を成功させた例が幾つもある。富山においても県、市、民間企業が協力、北陸新幹線の開通を見越して、廃線になっていた路線を新感覚の「富山ライトレール」へと変貌させた。計画から開業までわずか3年。市民の意識も驚く程高い。
天文館周辺はマイカー乗り入れ禁止にしてはどうか?派手ではないが、緑・歴史・文化・商業施設が織りなす、最先端の空間が創出される筈だ。ヴェニスの様に「車がいない街」として世界中から注目が集まることだろう。
昔の観光パンフレットを見ると、県内全域に張り巡らされている鉄道網が輝やいている。近所にも南薩線が走っていた。現存していれば、観光資源としての価値は計り知れない 。かつてあった駅舎の周辺には、その残像とも言えるドラマを感じる事が出来る。あの時代はもうやって来ないのだろうか。ダラダラと移動する車社会と違って、鉄道で出かける時には、待ち時間も含め皆「折り目正しい旅」を楽しんでいたのではないか。私の夢は天文館で飲んだ後、市電で自宅まで帰ることなのである・・・。
***
追記:この話題については随分前から何度も取り上げてきたので「またか〜」と思われる方も多いと思います。一昨年から「ライトレール・トランジット」をイラストのシリーズとして展開しており、鹿児島では多くの方に観て頂きました。また、鹿児島大学の学生が中心になって計画した、まちづくりについてのシンポジウムにも参加しました。これから、高齢社会が加速して自動車を運転出来る人口は減り続けます。今のうちから声を大きくして取り組むべき課題です。我が家でも現在、二台ある自家用車のうち一台を手放しても大丈夫かどうか実験中。バスと鉄道を使って鹿児島市内に出かけると、確かに車よりも時間がかかります。しかし、待ち時間はボーッとしている訳ではなく、読書や仕事、メールの送受信に充てられる。反対に運転中は、ラジオや音楽は聴けるけど、基本的には交通安全の事しか考えられない筈。みんなが公共交通機関に切り替えるだけで、街全体の偏差値があがると思うんです。車にかかる維持費・・・車検や保険、税金やガソリン代、駐車場代などなど・・・これらをそれぞれの家庭がこまめに支払っているという構図も最近では信じられなくなってきています。全てまとめて、交通のプロにお任せする方がスマートなのではないでしょうか。