
吹上浜クリーン作戦に参加してきました。朝7時から9時の二時間ほど。大雨の影響で、川から流れてきた竹が、膨大なゴミとなって漂着しているので、集めて、その場で燃やします。海亀が産卵をする季節でもあるため、海岸に障害物があると上陸出来ないのです。ペットボトルや空き缶のゴミも相変わらず目立ちますが、こういう悪い習慣は、いつになったらなくなるのでしょうか・・・。

吹上浜クリーン作戦に参加してきました。朝7時から9時の二時間ほど。大雨の影響で、川から流れてきた竹が、膨大なゴミとなって漂着しているので、集めて、その場で燃やします。海亀が産卵をする季節でもあるため、海岸に障害物があると上陸出来ないのです。ペットボトルや空き缶のゴミも相変わらず目立ちますが、こういう悪い習慣は、いつになったらなくなるのでしょうか・・・。

見慣れた市電が「パトカー仕様」になっていました!車両全体に広告になっている—いわゆるラッピング広告はよく見かけますが、このように「他の乗り物にカモフラージュしている」というコンセプトは新鮮ですね。パトカーに限らず、映画やアニメで出て来た特殊車両に似せるというのもアリだと思います。スター・ウォーズの反乱軍風とか、バットモービル風とか・・・。

その友人は、高知でひと仕事した後、フェリーで九州入りしたのだそうだ。大分から南下して鹿児島に。渋いルートです。
お土産に頂いた野村煎豆加工店のミレービスケット。友人は「高知の人はみんな、このビスケットを食べて育ったらしい」と言っていました。それほどポピュラーなお菓子なんですね。
「昭和の頃から変わらぬデザイン」と表記されていますが、パッケージ自体は新しいと思います。

今年は早めに一杯目をいただきました!相変わらずの美味しさ。関東方面から友人が遊びに来ていたので、鹿児島市内中心部から高速に乗ってGO~。この友人、鹿児島へ来たのはもう何回目でしょうか。鹿児島観光リピーターの多くは、観光名所ではなく「個人の力を感じるお店」を目指してやってくる事が多いと思います。

7時30分。小学校二年生の長男を車道まで見送る際、クワガタとカブトムシをゲット!
女の子にとっては「固いゴキブリ」と呼ばれる事もあるらしいですが、男の子にとっては宝石の様な意味があります。
実際、このクワガタのテカリ具合って、ものすごくキレイです。
***
いよいよ夏休みが近づいてきました。
まだ予定がたっていない方は、是非鹿児島にお越し下さい〜!
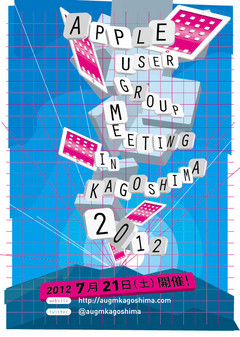
Apple User Group Meeting in Kagoshima July 2012
今年も開催されます。
内容は、一度出席された方には説明するまでもありませんが、南九州最大のApple関連イベントとなっております。
同じ日置市在住で国際的に活躍している平田みずほさんの「音の編集イロイロ」も見逃せません。私オーテマも3年ぶりにデモを行います。再稼働反対デモではなく、illustratorCS6のデモです〜。
あと30席ほど残っている様です。お申し込みはお早めに〜。
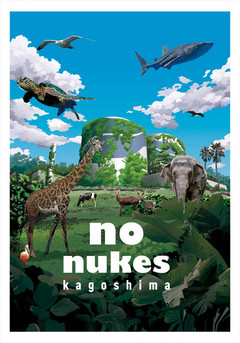
イラストレーターは、あまり好きな言葉ではないけど「商業美術」と呼ばれる世界の仕事。このポスターを描くときも、依頼してきた方から心配されて「仕事が減るかも知れないけどいいですか?」と言われた。エネルギー関連の仕事がなくなるリスクを負うことになるのでは?という考え方に基づいた助言だ。マスコミと電力会社の関係についてのウワサも耐えないけど、本当にそうなのかどうか、庶民である僕には解らないし、単なるウワサだと信じたい。この絵は、誰かを批判するものではなく、一緒に未来のエネルギーの事を考えたいという気持ちで描いた。「仕事がなくなるよ」という心配は鹿児島移住を決断した時にも言われた。しかし、実際に行動してみると、その先で「これまでの倍以上の仲間が待っていた」というのが、僕の半生で得た貴重な体験、結論だ。変わることを恐れてはいけない。時代の流れは止められない。これからは自然エネルギーの時代だ。無用な対立は避けて、みんなで考えて変える。そういうことだと思うのです。

美術をかじっているハシクレとして、これだけはどうしても伝えたいと思いブログにアップします。
大学の先輩で、桜島に移住して22年・画家の野添宗男さんが中心となり(代表:関好明さん)、今回の鹿児島県知事選に出馬するお二人に公開質問状を送った件です。鹿児島の風景として貴重な存在だった「西田橋」に関するものです。告示日までの回答を求めましたが、現職側は公開質問状の受け取り自体を拒否。新人の向原さんはきちんと回答してくださいました。「ただの人気取り?」だと思われると困りますが、向原さんはずっと昔から、鹿児島の石橋については深い思い入れがありました。美術家で、現在は十和田市現代美術館副館長も務めていらっしゃる藤浩志さん(僕も何度か展覧会でご一緒させて頂きました)と一緒に、1996年「たけのはし」という絵本も出版しておられます(南方新社は、向原さんが代表を務める地元の出版社)。エネルギーだけでなく、鹿児島の歴史や文化、美術について考えるときも、お二人の姿勢の違いは明らかなのです。
***
長くなりますが、公開質問状の内容と、向原さんの回答を以下に記しておきます。
***
公開質問状の内容(大まかな内容は変更されていませんが、最終的な言葉遣いについては一部変更されている可能性があります)
2011年の国難から二年目の今夏、鹿児島県政のリーダーを目指し次期県知事に立候補されることに敬意を表します。
私たちは1993年8月のいわゆる「8.6水害」において、当時の鹿児島県行政によって「水害の要因となった」という理由で、甲突川上から
撤去・移設された県重要文化財「西田橋」をふくむ「五石橋」などの歴史遺産の現地保存を求めた市民運動の一環(ひとつ)、美術家が
中心となって取り組んだ「西田橋を拓本で残す会」であります。
(私たちのこれまでの活動については新聞・テレビ等で広く知られるとおりですが、添付資料をご参照ください)
この度の県知事選挙にあたり、立候補された御二人に、次の点について公開質問という形をもって、私たちの長年の願いをお届けさせて
いただきます。
ご多忙の極みと存じますが是非ご検討いただき、ご回答をお願いいたします。
1.西田橋の現地保存運動のなかで生み出された「西田橋」の拓本原本と復現(元)パネルを「二十世紀の鹿児島県民が創りあげた文化財」と
して鹿児島県行政によって保存・継承していただくこと
1.右の条の回答につきましては、公示日までに書面によってお願いいたします。
私たちは拓本活動にあたり、鹿児島県と協議を持ち、その結果認められて、工事を請け負った小牧建設も入れた「三者協定」を締結して
始めることが出来たのです。
現場における拓本作業は、1996年1月13日に開始し、足掛け8ヶ月の時日(実動107日)とのべ2,000人を超える県内外の人たちの協同によって
「西田橋」の上・下流側面と内部構造など可能な限り、ほぼ全面にわたって写し採りました。
さらに三年の歳月をかけて復現(元)作業は取り組まれて、畳300枚分のパネルに納め、全長57米 高サ9.5米に及ぶ下流側面図は完成しました。
それは見事に現地に架かっていた「西田橋」を彷彿とさせるものに仕上がっています。
しかしそれは単なる写しに終わっているのではなく、その巨大な拓本を作っていく過程では様々な才能の創意工夫が集積され、期せずして
現代の美術状況にあって新たな価値観を創りあげているのです。
「西田橋の拓本」は二十世紀の鹿児島県民の郷土愛や誇り、感性が結晶となった「新しい文化財」であるといっても過言ではありません。
その美術的レベルは著名美術評論家から「現代美術のトップをいくものだ」ときわめて高い評価を得ているのです。
私たちはこれまでも「西田橋の拓本」が鹿児島県によって保存・継承されることを求め続けてきました。
1999年10月5日、県文化振興課における交渉では、当時の課長から「その方向にむかって努力します」という回答をいただいたのですが、
後任課長によって否定されたまま、その後有効な協議をもつことなく現在に至っています。
しかしその後13年間、私たちは三回の拓本全面公開をするなどしてアピールを続けながら、市民個人の協力を得て、原本と復現(元)パネルを
守り通してきました。(この間、拓本活動に関わった人たちは既に1万人を超えています)
自然災害を多く経験し、原発をかかえる当県においてこそ、将来の行政としてのあり方として、主体的で創造的視野に裏付けされた新しい
発想がなによりも必要とされるのではないでしょうか。
そのことが、県行政と県民間の信頼関係をより深め、魅力ある鹿児島県を発現させる力になると信じるからです。
平成24年6月13日 西田橋を拓本で残す会
***
2012年6月19日
西田橋を拓本でのこす会 代表 関 好明様
原発のない鹿児島をつくる会 代表 向原よしたか
前略
6月13日に書面にてお尋ねのあった件につき、次のように回答いたします。
拓本原本と復現(元)パネルは、鹿児島県が保存・継承するべきものであると考えております。
甲突川に架かっていた五石橋は、幕末の薩摩の歴史遺産であり、アーチ式石橋の最高傑作といわれるほどの石造技術の結晶でもありました。現地保存を望む多くの県民の願いは、県当局によって踏みにじられ、移設が強行されました。その記憶は消えることがありません。歴史的環境の「移設という名の破壊」は、鹿児島の美意識と品位を損ない、その心根を深いところで傷つけたと考えています。
西田橋の拓本は、文化破壊をよしとしない人びとの思いが結実したものであり、それ自体が保存・継承すべき価値をもつものだと考えます。よって上記の通り回答いたします。
草々
***

事務書開き、総決起集会、伊集院での講演、地元永吉での講演(企画も含む)、中央駅前の講演、昨日の坂口恭平新総理とのトークイベント(出演)、中央駅前のライブペインティング(制作)・・・。
もう、追っかけ状態。
「人」の事を追いかけたのは、一体いつ以来だろう?と思いだしてみると、1994年、スティーリー・ダンの初来日公演以来だった!
ムコハラさんとスティーリー・ダン、両者の存在は全く違うが、強引に自分の中で共通項を探ってみる。
:::
スティーリー・ダン・・・「ミュージシャンズ・ミュージシャン」と呼ばれるだけの豊富な音楽知識や、複雑なコード進行と演奏能力。ニューヨーク製ウエストコースト・サウンドと呼ばれる絶妙なバランス感覚。SFモチーフが多い未来志向。信者多し。シャイ。
向原よしたかさん・・・「本好きのための本」を出版し続けるだけの農業やエネルギー、民俗学への豊富な知識。農業に明け暮れる日もあるし、出版業へと専念する時もある、絶妙なバランス感覚。僕たちがこれから知りたい事を知っている未来派インテリ。信者多し。シャイ。
:::
そんな訳で!
向原さんの事が好き!