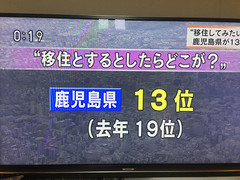全国ニュースでも取り上げられた様ですが、自宅から南へ30分ほどのところ(南さつま市金峰町)に、マッコウクジラ6頭が打ち上げられました。慌てて現場に行ってみたのですが、すでに潮が満ち始めており近づくことは出来ませんでした。鹿児島水族館の方々によって、下顎が切り取られていました(写真上)。歯を調べると年齢が解るということで、研究資料として持ち帰るのだそうです。それにしても実に不思議な形をしています。
「この様な出来事があると、地震との因果関係をよく質問されるが、実は吹上浜だけでも年間に1000頭は打ち上げられている」と水族館の方がお話されていました。日常茶飯事であるから、心配しても仕方がないということなのでしょう。
クジラがどうして集団自殺の様な行動をとるのか、まだ分かっていない様ですが、いずれは、クジラの言葉が解明されて人間が何かの手助けを出来る日が来るかも知れません。死んでしまったクジラには申し訳ないと思いますが、こんな出来事があって「街はもう大騒ぎ」という感じになっていたんです。車で乗り付けた時には「クジラ見学」と書かれたプレートを持って立っている方(おそらく役場の職員さん)もいらっしゃいました。普段は閑散としている吹上浜ですが、クジラとの対話が実現すれば賑わいを取り戻せるかも知れません。