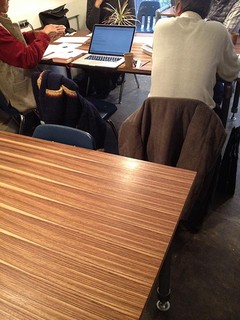Adobe Creative Cloudが何かの機会にログアウトしてしまって・・・再度ログインを試みたものの、パスワードが違うということで、リセット→再設定したんです。今度はうまくログイン出来ましたが、クラウド上にあるファイルが全て消えていました。どのファイルも手元(ローカル)に残っているのでダメージは殆どないのですが、駅に忘れ物をしてきてしまったという様な感覚があります。最近、クラウドに保存することが当たり前になってきていますが、こうした事態はいつ来るのか予測がつきません。そういう意味ではハードディスクの故障と同じと言っていいと思います。(こちらでは見られないけど、どこかにデータが残っているかも?という意味ではクラウドの方がタチが悪いかも。)いずれにしても、デジタルデータの管理に正解はない様です。
写真は12月18日のもの。桜島冠雪。