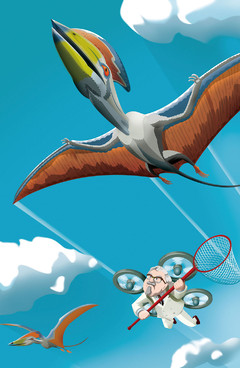今回の主役4名は、オープニングパーティーの意味を理解していないようだった。というより、行った経験がないと言っていた。搬入の日「明日は普段着で来る予定」と言っていたメンバーの一人に「そんな考えではダメだ」と注意した。
招待する側であり、作品を売る側であるから、少なくともスーツを着用するようにと言った。本当はスーツではなく、ステージ衣装のような、あるいは極端な仮装のような姿がいい。とにかく、ウルサめに「作家たるものは論」を色々と説明したので、当日、メンバーの一人がそれぞれのテーマカラーの蝶ネクタイを作ってきてくれた。これは嬉しかった。
とにかく、人に見てもらってナンボの仕事だ。それはもちろん、作品だけでなく作家自身を見られることにも繋がっている・・・。
地味なシャツを着てきた1名には、オープニング直前に僕が着古したリンゴ柄のシャツをプレゼントした。
パーティーには想像以上の人たちが来てくれた。みんなが祝福してくれていた。本当に良かった。この場の空気が何を物語っているのか、彼らに伝わっているといいな。
色々と書いていて、自分がジジイの立場であることを実感しています。