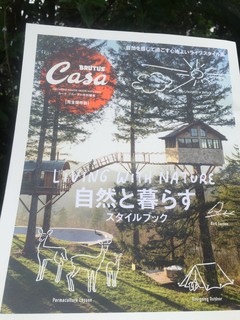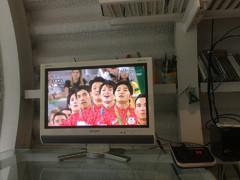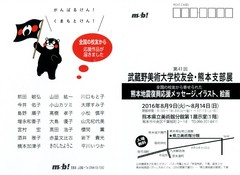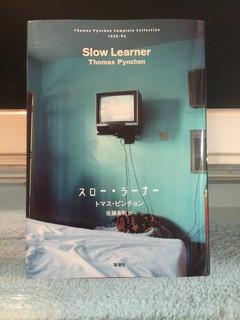網戸にカマキリが張り付いていたので、そのまま部屋にお越しいただき、撮影会となりました。
こちらは友好的な態度で誘ったつもりだったのですが、最初から威嚇のポーズ。羽を広げて尻尾をグニュっと反らせています。本気!自慢のカマは顔の両脇に収めて、ボクサーがガードをしているかのよう、パンチを繰り出す直前の態勢なのでしょう。それにしてもカマのギザギザは、すごい形をしています。割り切られているデザインというか。
春は小さなカマキリを良く見かけますが、これから冬場にかけて、夏場を乗り切った大きなカマキリを何度となく目にすることになります。悪者キャラの印象が強いカマキリくんですが、必死に子孫を残そうと日夜戦っている姿勢が伝わってきた撮影会でした。