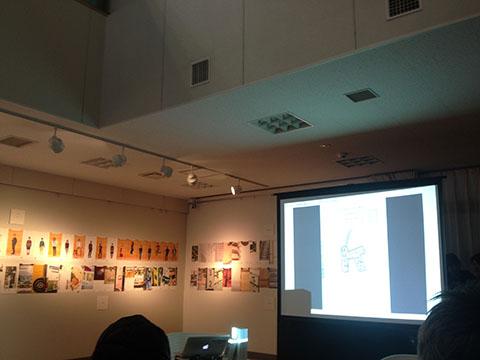カゴシマ トーキョー 断片
かごしま文化情報センター(KCIC)の主催する 「カゴシマ トーキョー 断片/出版記念トーク/地域 ≡ デザイン/松本弦人×ナガオカケンメイ」に出かけてきました。松本さんがナガオカさんの取り組みについて、DEPT(そのほか文化屋雑貨店やCISCO)といった80年代の東京で起こっていたことと繋げて話をする場面は面白かった。「バブル期ちょっと前=昔の東京の風景」と「今の不景気下=地域の状況」は全く違うものであるかと思いきや、同じ構図で語れるんだなあと思った次第。また、ナガオカさんの「デザインという言葉が(デザイン家電やデザイナーズマンションに見られる)マジックワードの様に使われているのではなく、デザインと呼べないものをデザインと呼べるようにならなくては」という話も、何度か違うカタチで耳にしたことはあったと思うけど、納得のいく話であった。
昔からデザインをやっている人たちは、デザイナーという仕事にもデザインという言葉にも、どこかで疑いを持ち始めている。ここのところ、ずっと・・・。キュレーションされたものしか目に出来ず、それをオシャレと勘違いして群がり、模倣し、結果として短命なデザインが氾濫することに懸念を抱いているからだと思う。地域性を自分たちで漂白してしまう。若い人は自分の審美眼や哲学を経験から生み出すことがしづらい世の中だ。ナガオカさんは、鹿児島大学の学生に「篭ることが必要」とアドバイスし、松本さんは「デザインは徹底的に見ないようにしている」と言った。とても重要なことだと思う。
***
お二人の行動は、結果として地域を編集してしまっている訳だけど、それはお二人とも勿論確信されており、松本さんが何度も「功罪」という言葉をナガオカさんに投げかけていたのが印象的だった。結局のところ、お二人のような孤独で角の立ったクリエイターが鹿児島から立ち上がれる時代にならないと、いつまでたっても鹿児島は独自性を見出せなないまま都会の人に頼ることになるのであろう。